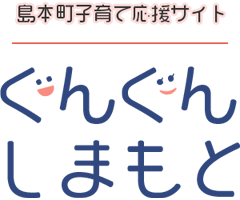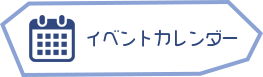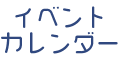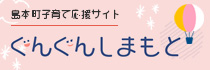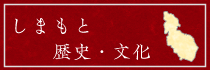本文
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
施設等利用給付2号または3号認定を受けるには、保護者のいずれもが、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
| 事由 | 内容 | 認定の有効期間 |
|---|---|---|
| 就労 | 月に64時間以上労働することを常態としていること | 対象児童の小学校就学まで |
| 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、または出産後間がないこと。 | 認定起算日から出産日の8週間後の翌日が属する月の末日まで(注1) |
| 疾病・障害 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。 | 対象児童の小学校就学まで (医師の証明期間等に基づく期間内) |
| 介護・看護 | 長期にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護し、または看護していること。 | 対象児童の小学校就学まで (介護及び看護が継続している期間内) |
| 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 | 認定起算日から60日が経過する月の末日まで ただし、やむを得ない事由がある場合は90日が経過する月の末日まで |
| 就学 | 就学(職業訓練を含む。)していること。 | 保護者の卒業の日が属する月の末日まで |
| 育児休業 取得時 |
育児休業取得時に、既に在籍園の預かり保育を利用しており、預かり保育の継続利用が必要であること。 (幼稚園等入園と同時の、育児休業の要件での認定はできません。) |
認定起算日から育児休業の対象となる子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで。 ただし、やむを得ない事由がある場合は育児休業の対象となる子どもが2歳に達する日の属する月の末日(2歳に達する日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、その年度の末日)まで |
| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。 |
対象児童の小学校就学まで(事由に必要な期間) |
| 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがあること。 |
対象児童の小学校就学まで(事由に必要な期間) |
| その他 | 上記以外に保護者が当該児童を保育することができない事情がある場合は、子育て支援課にご相談ください。 | 町長が必要と認める期間 |
(注1)妊娠中かつ保育を必要とする状態(妊娠に伴う、体調不良により保育ができないなど)である場合は認定を受けることが可能となります。ただし、産前6週前の日が属する月の初日(多胎児妊娠の場合は、産前14週前の日が属する月の初日)からは保育を必要とする状態であるとみなします。
保育要件確認書類
| 要件等 | 保育要件確認書類 | 証明者等 | |
|---|---|---|---|
| 就労 | 下記以外の場合 | 就労証明書 | 雇用主 |
| 自営業の場合 (中心者) |
就労証明書 | 自営業者自身 | |
|
開業届 または 直近年分の確定申告書の写し |
- | ||
|
自営業手伝いの 場合 |
就労証明書 | 自営主 | |
| 内職の場合 | 就労証明書 | 発注元または本人 | |
|
発注元との委託契約書の写し ※就労証明書を本人が記載した場合のみ |
- | ||
|
妊娠・出産の場合 |
母子健康手帳の「子の保護者」欄と「分娩予定日」欄の写し | - | |
|
上記書類に加え、疾病等・介護・看護・出産を理由とする場合の証明書 ※産前6週前の日の翌日が属する月の初日より前から認定を希望する場合のみ |
医師 | ||
|
病気・障害等の場合 |
疾病等・介護・看護・出産を理由とする場合の証明書 | 医師 | |
| 各種手帳等の写し | 必要に応じて | ||
| 同居親族の介護・看護の場合 | 疾病等・介護・看護・出産を理由とする場合の証明書 | 医師 | |
| 介護・看護状況申立書 | 申請者 | ||
| その他、介護状況が分かるもの | 必要に応じて | ||
| 同居親族の施設通所を介添する場合 | 介添証明書 | 学校(施設)長 | |
| 求職活動中の場合 |
求職活動誓約書 ※就労先が決定した場合、就労証明書の提出が必要。 |
求職者本人 | |
| 就学の場合 | 在学証明書(任意の書式) | 学校(施設)長 | |
| 年間のカリキュラムの分かるもの | - | ||
| 時間割の分かるもの | - | ||
| 育児休業の場合 |
就労証明書 ※育児休業期間欄に証明のあるものに限る |
雇用主 | |
| 災害復旧 | 罹災証明書 または 被災証明書 | 自治体等 | |
| 虐待・DV | ※担当課へご相談ください | ||
| その他 | |||
必要な申請
【新規で申請する場合】
- 施設等利用給付認定の申請
- 保護者の人数分の保育要件確認書類
- 代表保護者の本人確認書類
※個人番号(マイナンバー)確認書類の提出が必要となります。
【現在受けている1号認定から、2号または3号認定に変更する場合】
- 記載内容変更の届出
- 保護者の人数分の保育要件確認書類
- 代表保護者の本人確認書類
※個人番号(マイナンバー)確認書類の提出も必要となります。
※令和6年度以降に入園される方の申請はオンラインとなります。次のURLまたはQRコードから申請フォームにアクセスして、手続きしてください。なお、オンライン申込フォーム(Logoフォーム)は、システム停止を伴う定期的なシステムメンテナンスや障害発生により、アクセスできない場合や利用できない場合があります。予定されたメンテナンススケジュールや障害の発生状況などの最新情報は、以下のページから確認することができます。
(メンテナンススケジュール)
https://publitech.fun/logoform_maintenance<外部リンク>
(障害の発生状況)
https://publitech.fun/logoform_failure<外部リンク>
■施設等利用給付認定申請(令和6年度以降に入園する児童に限る)
<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/323357<外部リンク>
■記載内容変更(令和6年度以降に入園する児童に限る)
<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/374850<外部リンク>
<QRコード>
添付書類等
令和6年度以降に入園される児童にかかる申請等は、オンラインにて行ってください。その際、各証明書等のアップロードが必要となりますので、あらかじめご準備ください。