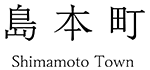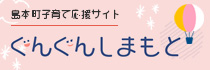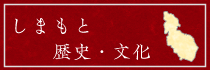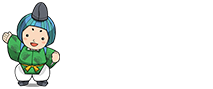本文
須恵器ってなあに
今回の文化財こぼれ話は、島本町の発掘調査でもたくさん発見されている青灰色(せいかいしょく)で、かたい土器(どき)、須恵器(すえき)についてです。
島本町の須恵器といえば、【須恵器の大甕(おおがめ)】です。
なぜなら、須恵器の大甕は、その歴史的価値によって町の文化財に指定され、JR京都線 JR島本駅前にある島本町立歴史文化資料館(れきしぶんかしりょうかん)の入り口に展示されている、町の須恵器の代表だからです。
この大甕は、今からおよそ1300年前、8世紀頃(奈良時代後半~平安時代初頭)に作られたと考えられる、液体などを保存するための容器です。

大甕という名前のとおり、高さ105.0cm、最大胴部径が107.8cm、容量は522.6lにもなる巨大なもので、500mlのペットボトルで考えると、約1045本分にもなります!
保存状態は良好で、上部の口の部分が二箇所欠けただけの、ほぼ完全な形で残されています。
この大甕は、今からおよそ30年前に宇治川、桂川、木津川の三川(さんせん)が合流する地点の中洲(なかす)(画像★位置)で、夏の水量が減った時期に川床(かわどこ)から姿を現しました。

船の積み荷が落ちたのか、あるいは岸から、何らかの理由で流れてきたのだろうと考えられます。
須恵器は、この大甕のように、液体などを保存するのに、もってこいの容器でした。
須恵器は、元々、5世紀前半に朝鮮半島(ちょうせんはんとう)より伝えられました。
当時の日本のやきものにはなかった最新の技術が、須恵器には使われていました。
その技術とは、登り窯(のぼりがま)で焼くことと、轆轤(ろくろ)という回転する台を使って、遠心力で形を作り上げることでした。
登り窯というのは斜面を利用して作った幅2m、長さ10m程のトンネル状の窯で、熱を逃がさずに高温を保つことができ、窯の入り口をふさぐことで、窯内の酸素の供給をおさえて、やきものの粘土の中の酸素を使わせます。粘土の中には酸化鉄があり、酸素を奪われた酸化鉄は、鉄成分となり、須恵器独特の青灰色を発色しました。
それまでの野焼きの土器とは違う、青灰色でかたく、水もれしない土器が誕生したのです。
須恵器は、古墳時代に代表されるマツリの道具、椀(わん)や皿などの食器、擂鉢(すりばち)などの調理道具、硯(すずり)などの文房具といった様々な種類が作られましたが、時代が下るにつれて、種類は限られるようになり、中世(12世紀頃)には、鉢や甕(かめ)が主なものになっていきました。
これらは、町内広瀬5丁目の平安時代の遺跡から出土した須恵器です。


今では、やきもの、陶芸(とうげい)と聞くと、窯や轆轤をすぐに思い浮かべられるのではないでしょうか。
しかし、須恵器が伝わる前の日本では、誰も知らない技術だったのです。