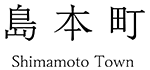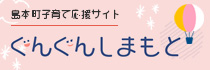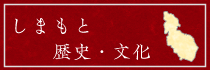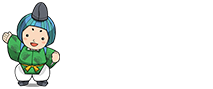本文
土師器の歴史
今回の文化財こぼれ話は、土師器(はじき)の歴史についてです。
土師器は古墳時代以降に出現し、前の時代に作られていた「弥生土器(やよいどき)」を受け継いだ、素焼きの土器です。
約700~800度の温度で、野焼きで焼かれたため、色は赤色や黄かっ色で、軟らかい土器であることが特徴です。
土師器は、水などの液体を長期間入れておくことはできませんが、火や熱には強いことから、その特性を活かし、甕(かめ)、羽釜(はがま)など、今でいう鍋として煮炊きに使用したり、あるいは杯(つき)、高杯(たかつき)などお供えの器(うつわ)や食器として利用したりしました。
(写真 土師器甕:はじきかめ)

(写真 土師器羽釜:はじきはがま)

奈良時代になると、人々は土師器の杯や皿を、明かりをともすための灯明具(とうみょうぐ)として用いました。
油を入れて灯心(とうしん)を浸して点火するため、灯心の燃えかすやススが付着し、一部が黒くなった土師器が見つかることがあります。
(写真 灯明皿:とうみょうさら)

平安時代になると、貴族たちが土師器の杯や皿、高杯(たかつき)を宴会や祭礼に用いました。土師器は生産効率がよいため、一回きりの使い捨てで用いたようで、貴族たちに幅広く利用されました。
土師器は中世以降も、宴会や祭礼などの場で使用されます。中世の後半になると、手づくねで作られた土師器皿として「かわらけ」が出現します。土師器皿の大きさは6cm程度の小さいものや、15cmを超える大きなものも作られ、使われていたようです。
(写真 さまざまな土師器皿)

特に、祭礼の場では、赤色や黄かっ色の土師器皿ではなく、特徴的な「白い土師器皿」を使用していたと考えられます。
(写真 白い土師器皿)

また、大量に使い捨てられた土師器皿が土器溜まり(どきだまり)として発掘調査で見つかることもあります。かわらけは灯明具としても使われ、近世まで使用され続けたことが出土遺物から分かります。
(写真 発掘調査で見つかった土器溜まり)

今となっては土師器と日常生活で接する機会は少なくなりました。建築工事の安全を願うため、地鎮祭(じちんさい)のお供えの器として「かわらけ」を使用したり、また一部の神社では神事や「かわらけ投げ」でみられるように、土師器は祝事や祭礼、祈願に使う特別な器として、今も受け継がれているのです。