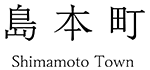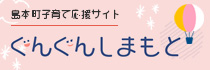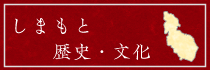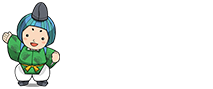本文
広瀬遺跡の発掘調査について(2)
不定期で更新しております文化財こぼれ話ですが、今回は広瀬遺跡の発掘調査についての2回目となります。
本町においては、令和5年度に計3件の発掘調査を実施しました。その中から、広瀬遺跡(HS23-8 大海道)発掘調査について紹介したいと思います。
遺跡や古い時代の地面は、後の時代に起きた洪水などにより土砂がたまっていくため、大半が地中深くに埋まってしまいます。発掘調査ではまず、遺跡が埋まっている深さまで、現代の土をバックホーなどの重機で取り除きます(表土掘削・ひょうどくっさく)。
(写真 表土掘削作業風景)
調査では、浅いところでは地表面からの深さ約40cm、深いところでは深さ70cmのところで、土器などを含む昔の土(遺物包含層・いぶつほうがんそう)を確認し、これより下は人の手によって慎重に掘り進めていきました。
遺物包含層を取り除くと、地面に丸や四角などの形が見えてきます。写真では、白い線を引いて分かりやすくしていますが、色の違いや含まれる土の違いを探していきます。
(写真 遺構検出状況)

これらは昔の人が地面に掘った建物の柱穴や溝などの痕跡で、遺構(いこう)と呼ばれます。今回の調査では遺構が合計300個近く見つかりました。
(写真 遺構掘削)

(写真 全景写真)

調査範囲北側では、土器が埋められた穴が2個見つかりました。一つは鎌倉時代の土器(瓦器椀・がきわん)が埋められた穴です。
(写真 北区 瓦器椀出土状況)

もう一つは平安時代の土器(土師器甕・はじきかめ)が埋められた穴でした。
(写真 北区 土師器甕出土状況)

調査範囲の中央では、平安時代の土器(土師器杯・はじきつき)が埋められた穴が1個見つかりました。
(写真 中区 土師器杯出土状況)

この他、調査範囲南側でも平安時代の土器(土師器・はじき、須恵器・すえき)が埋められた穴が見つかりました。
(写真 南区 土師器・須恵器出土状況)

調査範囲の南側で見つかった遺構は、ほとんどが柱穴で、これらは地面に直接柱を立てた「掘立柱」の穴と考えられます。
おそらく建物や塀などがあったと考えられ、何回も建て替えられたものと考えられます。
(写真 南区 遺構群)

柱穴の底には根石(ねいし)という、大きさが30cmもある石が置かれているものもあり、これは柱が沈んで建物が傾くことのないようにするためと考えられます。
(写真 南区 根石のある柱穴)

柱穴内には遺物が含まれており、多くが平安時代の後半頃(10~11世紀頃)の時期であることが分かりました。しかしながら、どのような建物であったのかについては現時点ではよく分からないことから、出土した土器だけでなく、柱穴の大きさや柱穴どうしの距離、また柱穴の配置について、引き続き調査していきたいと思います。