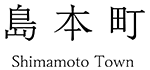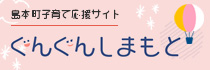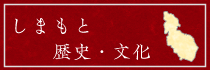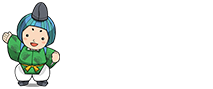本文
「道しるべ」をめぐる(2)
島本町の文化財を知っていただくために、企画展や刊行物に掲載することができなかった話などを連載していくことといたしました。
連載テーマなども統一せず、不定期で更新していきます。
今回は「道しるべ」の2回目、島本町山崎地区にある「道しるべ」を紹介します。
椎尾神社に建つ2本の「道しるべ」
JR山崎駅から西国街道を西に約600m歩くと東側にサントリー山崎蒸溜所の赤レンガが見えます。踏切を渡って緩やかな坂道を上っていくと椎尾神社の鳥居が見えます。
※椎尾神社-明治の初めまで「西観音寺」通称「谷寺」という大きな寺院でした。安永9年(1780)に刊行された「都名所図会」や寛政8年(1796)刊行の「摂津名所図会」にも掲載されています。しかし、慶応4年(1868)の神仏分離令により、僧侶は神職に転身、椎尾大明神を祭り、名を椎尾神社と改めました。寺院にあった文化財は分散され、島本町にはほとんど残されていません。
鳥居をくぐり、階段を上ると「道しるべ」は、拝殿下の広場に並んで建っています(1)。
1
〈1の写真向かって左側〉
【正面】
(写真は島本町立歴史文化資料館内展示 複製道標)
【正面】右 たからてら 三町 / てん王 九町
【右】・【左】・【背】 は文字なし
たからてら(宝寺)とてん王(天王山)へ向かう道を案内しており、もともと社標 椎尾神社碑の東側の山道(旧宝寺道)と参道の分岐点に建っていたと言われています。
※たからてら-宝積寺(通称宝寺)のことです。大阪府と京都府の境に位置し、由緒によれば神亀元年(724)、聖武天皇の勅願(天皇の祈願)によって、行基が開基したと伝えられています。
※てん王-大阪府と京都府の境にある山、天王山を指します。豊臣秀吉と明智光秀が戦った「山崎の戦い」の舞台として有名で、ハイキングや登山を楽しむことができます。
〈1の写真向かって右側〉
【正面】 【右】 【背面】 【左】




(写真は島本町立歴史文化資料館内展示 復元道標)
【正面】すくたからてら
【 右 】すくたにてら
【 背 】左 てん王道
【 左 】右 たにてら
この「道しるべ」も現在建っている場所ではなくて、椎尾神社の東側に建つ社会福祉法人 大阪水上隣保館の敷地内、礼拝堂付近(天王山と宝積寺に向かう分岐点)に建っていたと思われます。
ここで余談ですが・・・
昭和41年(1966)東京オリンピックの開会式を記念して制定された初めての体育の日(10月10日)に、島本町では第一回「天王山早朝ハイキング」が実施されています。
この日、午前6時に総勢約600人が中央公民館(当時は水無瀬川の左岸、東大寺地区にあり、今はありません)に集合し、JR山崎駅(当時は国有鉄道)の東側の踏切を渡って宝積寺を目指しました。仁王門を抜けて本堂から険しい山道を登り一路天王山の山頂へ!午前8時過ぎに到着しました。その後、この事業は時期や季節を変えながら22年間実施されました。
かつてはこの2本の「道しるべ」を頼りに人々は天王山を目指したり宝積寺に参詣したことでしょう。現在は移設され、忘れ去られてしまいましたが、一度訪ねてみてはいかがでしょう・・・
※一丁は距離で、約0.109キロメートル(109メートル)です。
※/(斜線)の記号は改行を表しています。