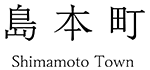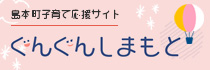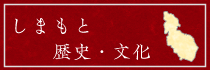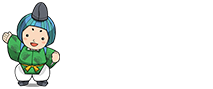本文
「道しるべ」をめぐる(1)
街道を歩く・・・
文化財こぼれ話も12回目、発掘調査に関係した話が続きましたが、今回は島本町内で見かける「道しるべ」についてお話します。
「道しるべ」は、江戸時代頃に設置されたものを多く見ることができます。街道の分かれ道などに建てられ、方向や距離などが記され、人が迷わず目的地にたどりつく案内役として、大きな役割を果たしてきました。
現代の道路の整備や改修等で、当初の場所から移動していたり、標示された文字の方角が目的地を指していないものもありますが、文字をたどることで、もともと建っていた場所を探し出すことができます。
また、道案内を目的としたものばかりでなく、地名・寺社名が記されたものや建てられた時期、建てた人の名前が刻まれたものもあり、様々な目的で建てられました。
西国街道沿いに建つ3本の「道しるべ」
1 桜井の道しるべ
JR島本駅の東側に国登録有形文化財「島本町立歴史文化資料館(旧麗天館)」があります。この資料館の東側には西国街道が通っており、京都に向かって歩いていくと、西国街道とJR京都線の踏切への分れ道に建っています(桜井一丁目)。

【正面】右 柳谷 / 左 西能宮(西宮) 楚うし寺(総持寺) 道
【右】施主名
【左】右 京 伏見 / 山崎 道
【 背 】慶応三丁卯年三月建之
【正面】 【左】 【 背 】



柳谷は、京都府長岡京市にある楊谷寺(ようこくじ)のことで『柳谷観音さん』として親しまれ、現在も眼病(がんびょう)平癒(へいゆ)の祈願所として、厚い信仰を集めています。
また、楚うし寺(総持寺)は大阪府茨木市にあり、西国三十三番札所として有名で、多くの巡礼者が参拝します。
道標が建てられた頃(慶応3年)は、この「道しるべ」から鶴ケ池(島本町役場)、若山神社を通り、尺代を経て柳谷観音に向かっていました。
※西国街道 京(京都)から大坂(大阪)を経ないで西国(下関、九州)に至る江戸時代の重要幹線道路。
2 東大寺の道しるべ
桜井の道しるべから、さらに西国街道を京都に向かい、水無瀬橋を越えて約0.1キロメートル歩くと、街道と柳谷観音へ向かう分かれ道に2本の「道しるべ」が建っています(東大寺一丁目)。
【正面】柳谷觀世音菩薩道 廣山書 / ㊞
【 右 】人名等
【 左 】明治三十四年六月 是ヨリ三十丁 発起人名
【 背 】 寄進者名等
この「道しるべ」も柳谷観音への道を案内しています。ここから三十丁(約3.2キロメートル)と記されていますが、道路改修等が行われ、現在は記された距離ではたどり着くことはできません。
【正面】官幣 / 大社 水無瀬神宮 左へ / 三丁
【右】・【左】は文字なし
【 背 】昭和十四年三月一日 水無瀬神宮洗心流建之
昭和14年(1939)は、後鳥羽天皇700年式年祭の年で、この年の3月1日には官幣中社 水無瀬宮が大社に昇格、同時に神宮と改称された年でもあります。
同じ「道しるべ」が大字山崎の国道171号沿い《【正面】官幣 / 大社 水無瀬神宮 西南 / 三丁(約0.32キロメートル)》・阪急大山崎駅前《【正面】官幣 / 大社 水無瀬神宮 西南 / 十丁(約1.09キロメートル》にもあります。
※式年祭 神道での法要の総称。
※洗心流 水無瀬神宮を家元とする華道の流派の一つ。

「道しるべ」の中には、長い年月風雨にさらされ、刻まれた文字を読むことが難しいものもあります。資料館では記録保存のために拓本をとり保管しています。また、とった拓本を用いて立体的に復元したものを展示しています。
普段は気にもとめず通り過ぎてしまう「道しるべ」も、記された文字や建てられた時期等をたどっていくと、様々なことが分かります。
今後も町内の「道しるべ」を紹介していきますので、楽しみにお待ちください。
※一丁は距離で、約0.109キロメートル(109メートル)です。
※/(斜線)の記号は改行を表しています。